相良三十三観音巡り
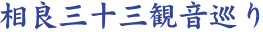 |
江戸時代中期、人吉球磨地方では観音信仰が庶民の間に広がりました。
33ヵ所に点在する霊場を、鈴を鳴らし、ご詠歌を唱えながら歩きつづけたといわれています。観音様に出会う巡礼には現在も多くの人々が訪れ続けています。 |
 |
| 普門寺観音 |
もともとは水上村湯山にあり、市房神社の修験場だったといわれますが、永正3年(1506年)に水上村岩野に移され、さらに湯前城内に移し再興したと伝えられています。
現在、聖、准胝、千手、馬頭、如意輪(十一面は亡失)の五観音です。
●相良三十三観音 25番礼所 | |
 |
| 上里の町観音 |
ご本尊は室町時代作の聖観音立像で、嘉永5年(1852年)に、久米の仏師弓削田市内が補修をしたという銘はありますが、後は不明な点が多いと言われています。
堂前の墓碑の裏には、「冬川の流れに落ちし枯葉哉」と彫った墓があります。 |
|
●相良三十三観音 26番礼所 | |
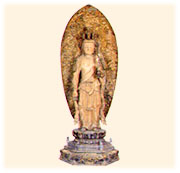 |
| 宝陀寺観音 |
宝陀寺の外観は、昭和49年に改修されましたが、内部の須弥壇や円柱などは、当時のままの姿で残されています。
木造十一面観音立像は、檜の寄木造で、頂上面を除く化仏、持物、光背、台座などは、後世になって修復されたと思われます。
県指定。
●相良三十三観音 27番礼所 | | | | |